KEYSTONE ILS CAPITAL
確かな未来を築く
災害リスクソリューション
保険リンク証券 “Insurance-Linked-Securities”
による災害リスクファイナンス
- ILSについて詳しく知る
- ILSの手配を検討(事業会社用)

保険リンク証券 “Insurance-Linked-Securities”
による災害リスクファイナンス
 SCROLL
SCROLL
限られた地域に世界有数の経済が展開する日本は、他国には例を見ない規模の自然災害リスクを抱えています。
国内では過去の経験を遥かに上回る規模の巨大災害の発生が想定されています。

直接的な物的被害を起点として、
企業活動停止、消費低迷、金融市場の動揺が連鎖的
に発生。
被災地を超えた経済圏全体への深刻な影響
広域自然災害は、資産の損壊やそれに伴う売り上げの
低下だけではなく、
事業活動に波及的な
様々な影響を与えます。
また、災害の規模が大きいほど災害による被害は
拡大し複雑化します。


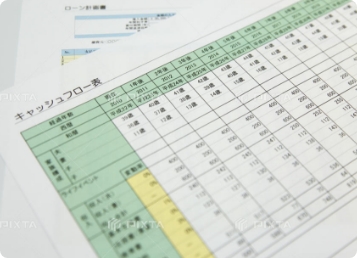
大規模自然災害による
経済的リスク発生の脅威は明らかですが、
国内の企業や自治体では対策の遅れが目立ちます。
日本の多くの企業や自治体は地震、台風、噴火などの大規模な自然災害リスクを日常的に抱えています。防災・減災の取組は積極的に行われていますが、リスクファイナンスはしばしば後回しにされているのが現状です。
しかし、これらの「目前の危機」に対処しないことは、実質的にリスクを抱える決断を行っていることと変わりません。いくら優れた防災・減災対策を講じても、完全にリスクをゼロにすることは不可能であり、残存するリスクへの備えが不可欠です。
適切な災害リスク対策は、①リスクの洗出し/評価、②リスクコントロール、③リスクファイナンスの三つのプロセスを経て実施されます。
リスクを低減するための措置を講じた後に残るリスクに対して、リスク保有(自らが抱えるリスク)とリスク移転(他者に移転するリスク)の最適なバランスを見つけ、それに基づく対策を導入することをリスクファイナンスと呼びます。



リスクコントロール(防災・減災)により解消できない経済的被害は、最終的には社会の中で誰かが負担する必要が生じます。リスクファイナンスによって、リスク保有とリスク移転の最適なバランスを検討し、それぞれに必要な対策を体系的に導入します。
リスク保有では資金繰りの手当てをした上で自らの資本で発生する損害を吸収します。一方リスク移転を行う場合、事前に補償料を負担することで有事に返済不要の補償が行われることとなります。
